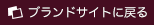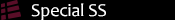

紆余曲折を経て、輝と付きあうことになった主人公。
新しい環境に慣れつつも、彼にはまだまだわからないところがあって……
Special SS『彼の手の中にあるものは』 著:松竹 梅
新しい環境に慣れつつも、彼にはまだまだわからないところがあって……
Special SS『彼の手の中にあるものは』 著:松竹 梅
「お疲れ様でしたー!」
仕事終わりの挨拶をして店の扉を閉めると、強い風が髪を乱した。道行く人々も驚いた顔をして、特に女性たちは「やだもう」なんて言いつつ服や髪を整えている。
同じく服を整え直した私は、けれど上機嫌でスキップしたい心境だった。
上着の袖口や襟についたフェイクファーが、次に訪れた微風でふわりと揺れる。真っ白なそれはクリーム色のコートを可愛く、少しだけ華やかな印象にしていた。
(ショップでの仕事は初めてだから心配だったけど、店長さんは優しいし、お仕事は楽しいし、しかもこの服も社割で買えたし……本当に幸先いいなー)
新しい職場が決まったのは、輝さんと付きあって間もなくのことだった。彼は私が働くのに反対みたいだけれど、私は現在の環境に満足している。
昔と違って、近頃は綺麗になろうと努力するのが楽しい。それに今着ている薄手のコートも、社員の特権で割引してもらえた。節約しつつも、可愛いものを着ていたい私にとっては、最適な環境と……
(いえる、よね?)
胸中で確認してしまうのは、今私たちの前にとある大きな問題があるからだ。だから浮かれてばかりもいられない。
「でも、落ち込んでいたって良いことはないもんね」
あえて声に出して、橙色になりつつある空を見上げた。次に決意を込めて両の拳を握り、一つ頷く。一瞬でも迷いに捕らわれないよう、勢いをつけて走り出した。
(輝さんも、そろそろ到着する頃かな)
今日は輝さんと一緒に帰る約束をしている。
新しい服を見せた時に彼が何と言ってくれるのか、想像するだけで頬が緩んだ。
数分後、輝さんとの待ち合わせ場所が見えて、段々と走るスピードを落とす。肩で小さく息をしていた私は、はっとしてショーウィンドウに視線を走らせた。乱れた髪や服の裾を直し「よし」と気合を入れる。直後、今度はそわりと落ち着かなくなって、意味もなく爪先を確認してみたりした。もう体中の至る所を見られた仲なのに、未だに恥ずかしいと思う気持ちが捨てられない。
(綺麗すぎる輝さんがいけないよね。うん)
勝手にいじけ、前髪をいじりだす。
その時、角の向こう側から憶えのある声が聞えてきた。
「――見かけたからって声かけてくるなよ。彼女に見つかる」
耳にしたばかりの声と、記憶の中の響きが一致しなくて、私は首を傾げた。
角の向こうで喋っているのは、たぶん輝さんだ。でも彼が、こんなに低く、不機嫌そうな声で話した時があっただろうか。
戸惑って動けずにいると、話し相手らしき人物がくつくつと笑った。
「そう冷たくするなって、俺たちマブダチだろ。それにこの間、貴重な情報をくれてやったばっかりじゃないか」
「はは、マブダチね。そうだな」
情報、と聞いて少しピンとくる。
輝さんの周りには友達……といっていいのかわからないけれど、彼いわく『色んなことを教えてくれる親切な人』とやらが複数いるらしい。今話しているのは、その内の一人だろう。マブダチと認めるくらいだから、輝さんも心を許している相手なのかもしれない。
(……いつかは、こういうことも聞けるのかな)
輝さんは極端なまでに自分の情報を開示しない人だから、いつも一緒にいるのに『らしい』なんて表現しかできない。だけどそれを承知で恋人になった手前、文句も言えず……。少しもどかしい思いをしていた。
そんな私とは対照的な、男性のやや興奮した声が耳に届く。
「なあなあ、あのDVD、グロくて最高だったよな。AVより抜ける」
ちょっと妖しい話になってきたぞ、と私は苦笑して眉をひそめた。偶然とはいえ立ち聞きしてしまっている時点で十分悪いのに、輝さんの性的嗜好まで知ってしまったら、なんというか……気まずいし申し訳ない。
輝さんが否定するか話を逸らしてくれればいいな、と思っていたら、
「あの程度の悲劇、少し探せばどこにでも転がってる」
やけに冷めた声が答えた。
(なんか、いつもとはすごい違うような気が……)
ますます困惑して、後ずさりもできなくなる。これ以上聞いてはいけないと頭の奥で警鐘が鳴り響いているのに、足が地面に縫いつけられてしまったみたいだ。
そうして胸を騒がせていた私は、次に聞こえてきた声で少しだけ肩の力を抜いた。
「それに今は、一緒に暮らしてる天使に夢中なんだ」
「ああ、綾瀬って女だろ」
「あはは。勝手に調べんなよ、殺すぞ」
声の柔らかさが聞きなれたものに近くて、ほっとする。ちょっといつもの言葉選びとは違うけれど、男同士の気安さがそうさせるのだろう。
緊張感から解放された私は、数秒遅れて『天使』という表現に意識が持っていかれた。
(もう、友達にまでそんなこと言ってるの?)
恥ずかしくて、嬉しくて、さっきとは違う意味で鼓動が早くなる。
私がもじもじと指先をいじっている内に、男性は別れの挨拶に入ったようだった。
「それじゃ、またな。次はその天使ちゃんに会わせてくれよ」
「はは、お前みたいなクズに?」
「キング・オブ・クズの輝サマに言われたくねぇな」
面白いネーミングだなぁ、と思いながら男性が去るのを待つ。やがて完全に足音が聞こえなくなった頃、私は一回深呼吸をして、あたかも走ってきたかのように角を曲がった。
「お待たせ、輝さん!」
「いや、全然待ってないよ。僕もさっき来たところなんだ」
きっと、私に気遣わせまいとしてくれているのだろう。彼の優しい嘘に、私は内心でお礼を言った。
「それじゃあ、帰ろうか」
「うん!」
差し出された手をとり、指と指を絡ませる。いわゆる『恋人つなぎ』をできる相手がいる現実に、感謝をした。
帰路には、あの橋――輝さんと私が出会った橋がある。
ふと感慨深い気持ちになった私は、沈み行く夕陽を眺めながら笑みをこぼした。
「どうしたの?」
問われて、少しだけ恥ずかしくなる。
(唐突にニヤついたら、誰だって不思議に思うよね)
慌てて俯いた私の頭に、優しく手が置かれる。
顔を上げれば、夕陽に染まった琥珀色の瞳が、ふわりと笑んだ。
「僕もだよ」
「え?」
「この場所に来る度に、君と出会えた幸せを噛みしめてしまう」
人の内心を察するのが上手い輝さんは、いつも絶妙なタイミングで応えてくれる。
心が通じ合っているような感覚に嬉しくなり、唇が勝手に笑みの形になった。だけど正直に反応してしまうのが悔しくもあって、私は半分照れ隠しで唇を尖らせた。
「私ばっかり読まれてる」
「君も僕の心を読んでいいんだよ?」
「読めないよ。だから私」
輝さんのことを、何も知らないのに。そう言いかけて、声を飲みこむ。
これじゃあ秘密を承知で付きあったのに、彼を批難しているみたいだ。
思い直した私は、なるべく婉曲な表現でお願いをした。
「いつかは輝さんのお友達とかにも……会えるかな。私も輝さんのこと、これから少しずつ知っていきたいんだ」
私としては、かなり勇気を出して言ったつもりだった。だから、きっと彼も真面目に答えてくれる――なんて考えてしまったのがいけなかったのかもしれない。
「はは、ごめん。僕、友達いないんだ」
あっさりと、満面の笑みで友達の存在を否定されてしまい、言葉をなくす。
(いけない、ここで無言になったら盗み聞きしてたのがバレちゃうよね)
頭の中では「じゃあさっきの人は?」とか「私は友達に会わせる価値もないのかな」とかネガティブな言葉がぐるぐる回っている。それが顔に出ないよう、精一杯の笑みを作った。
「あ、そう……なんだ」
「うん、そうなんだよ。でも今は、君がいてくれるから寂しくないけどね」
念押しのように言われ、胸に重石を置かれた気分になる。
(輝さんが自分のことを言わないのはわかってたけど、友達の存在まで否定されるとは思わなかったな……。なんで教えたくないんだろう)
承知していても、嘘をつかれるのは悲しい。そう落ち込んでから、はたと我に返った。
嘘をついているのは誰に、何に対してなのだろう。
マブダチと言ったあの男性にか、それとも私に対してなのか……もしくは、そのどちらもなのか。
「……」
大きく息を吸ったら、冷たい風が肺に流れ込んできた。そのせいか、ぶるりと体が震える。
私は寒かったからだと自分に言い訳をして、輝さんの腕に抱きついた。
すると、くすりと笑った彼が、私の頭頂部に口づけながら聞いてきた。
「そういえばその服、勤め先で買ったの?」
「うん。おかしいかな?」
「いや、すごく可愛いよ。可愛すぎて、今すぐ抱きしめたくなる」
「あ、ありがとう……」
好きな人に褒められると、どうしてこんなに落ち着かない気持ちになるのだろう。そわそわして、でも天に浮かびそうなくらい幸せで、変な笑顔になってしまう。それもまた恥ずかしくて俯けば、輝さんの言葉通り抱きしめられた。
「! だ、だめだよ、輝さん。こんなところで……」
「そんな可愛い反応されたら、もうこうするしかないでしょ」
人通りはあまりなかったけれど、車は次々と通り過ぎている。車内から見ている人たちは、きっと「バカップルがいる」と思っているだろう。
恥ずかしさで身じろぐと、私を抱きしめる輝さんの腕の力が強まった。息苦しさすら覚える抱擁は、単なるじゃれあいとは違う意図を感じさせた。
「輝さん……?」
「本当に君は、天使みたいに可愛い。だから僕は、君が飛び去ってしまわないように、いつも必死なんだよ」
「あ、あはは。何言ってるの、輝さん」
優しげに語る声は、どこか淡々としているようにも聞こえる。それがいっそう異様な雰囲気を醸していて、もっと息苦しくなった。
どうして私は、冗談でしかないはずの甘い囁きに、身を震わせているのだろう。
「あ、ごめん。少しファーがとれちゃったみたいだ」
高級品ではないから、買ってすぐにほつれることもあるだろう。気にしていないという意味で微笑むと、彼は舞い落ちるファーを手にとり、ぐっと握り込んだ。
夕陽で赤く染まったファーの先が、彼の指の間からはみ出している。
なんだか違うものを見ている気分になって、唾を飲んだ。
まるで、むしられた羽の一部みたいだ。
「素敵だね。……このコート」
疑いようもなく、コートを褒められている。
それなのに「素敵」という言葉がどこにかかっているのか気になった……。









2014.11.03
カウントダウンSS更新
2014.10.30
カウントダウンイラスト更新
2014.10.29
カウントダウンイラスト更新
2014.10.28
カウントダウンイラスト、SS更新
2014.10.24
「復讐ラジオ」、SS、ギャラリー更新